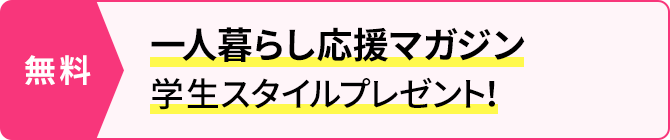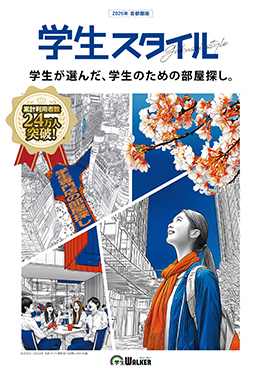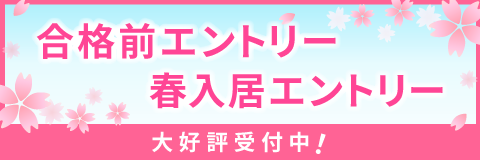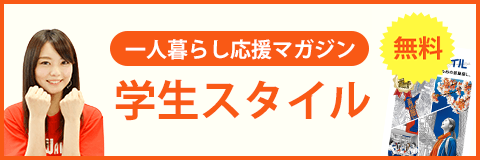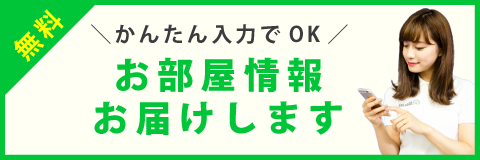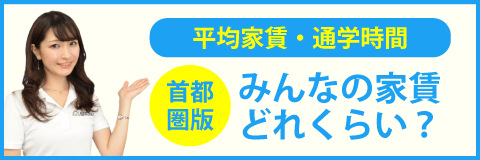- 学生ウォーカー トップ
- 大学入試の種類
- 一般選抜
大学入試の種類
一般選抜とは
大学入試改革により、一般入試は一般選抜に名称変更されました。
学科試験中心の選抜方式で、国公立大学と私立大学でスケジュールや受験科目数、仕組みなどが大きく異なります。
一般選抜 (国公立大学)
国公立大学の募集人員の約8割を占める一般選抜は、共通テストと大学独自の個別学力検査(二次試験)を組み合わせた選抜が行われます。1月の共通テスト後に志望校へ出願し、2-3月に大学ごとに行われる二次試験を受験し、共通テストと二次試験の得点の合計で合否が決まります。大学によっては基準の倍率より志願者が多くなったら二段階選抜という足切りを実施する場合も。
足切り=不合格ですのでそうならないよう共通テストの自己採点をして出願する学校を慎重に選びましょう。
- 国公立大学の一般選抜
「分離・分割方式」 - 国公立大学の試験は2月下旬に二次試験がある「前期日程」と3月中旬二次試験の「後期日程」があり、受験生はそれぞれの日程で1校ずつ出願できます(同じ学校でも違う学校でもOK)。一部の公立大学では「中期日程」が設定されている場合もあり、これを合わせると最大3回の受験チャンスがあります。
募集人員は前期:後期=8:2で圧倒的に「前期日程」の割合が高く、「後期日程」を廃止したり募集人員を縮小している大学も増えきています。また、「前期日程」で合格し入学手続きをすると「中期日程」「後期日程」での合格の権利を失うことになりますので、第一志望は「前期日程」で受験するのがスタンダードです。
- 国公立大学の一般選抜
教科・科目数 - 国公立大学の必要科目数は共通テストで6教科8科目、二次試験「前期日程」では2~3教科が一般的です(一部の難関大学では4教科を課す場合も)。「後期日程」では1~2教科に減らしたり、総合問題・小論文・面接などを課したり、二次試験を行わず共通テストの点数で合否を決めたりする大学があります。
入試配点比率も二次試験の配点を高くしたり、共通テストの配点を高くしたり、特定教科の配点を高くしたり大学によってさまざまです。入試科目や配点比率により受験対策は変わってきますので、はやめに自分の志望校の入試要項をチェックしておきましょう!
一般選抜(私立大学)
私立大学は国公立大学と違い共通テストの受験が必須ではなく、日程も入試方式も種類がたくさんあります。基本的には試験日が重ならない限りは何校でも受験することができ、同じ大学・学部を複数回受験することも可能です。2月上旬~2月中旬に試験が行われ、大学によっては2月下旬~3月にかけて後期日程(3月入試)が行われます。入試科目は大学によりさまざまですが3教科が一般的です。
- 私立大学の一般選抜の一例
-
- 個別学部入試(個別学部日程)・・・学部学科ごとに問題や日程が違う。オーソドックスな入試方式。
- 全学部統一入試(全学部日程)・・・その大学の全学部が共通の問題を使って同じ日に試験を行う。
- 共通テスト利用入試・・・共通テストの成績で合否判定をする。共通テスト前に出願締め切りの大学もあるので注意!
- 地方試験・・・地方の主要都市に試験会場が設けられる。
他にも特定の科目の配点が高い「特定科目重視型」や、教科数が少ない「少数科目型」、民間の英語検定や簿記などの資格保持者に点数を加点する「資格・検定試験利用入試」、共通テストと個別試験の成績を両方を使う「共通テスト併用型」など、大学ごとに多様な入試方式があります。
- 私立大学の一般選抜
一般的な科目数 -
- 文系学部・・・英語 + 国語 + 地歴公民 or 数学
- 理系学部・・・英語 + 数学 + 理科
一般選抜カレンダー
※一般的なスケジュールです。大学によって異なってくるので学校公式ページで必ず詳細を確認しましょう!


※2025年6月時点の情報を基に作成しています。
※正確な情報は、各大学の公式ホームページにてご確認ください。